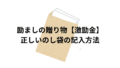日本全国で愛されている長崎の伝統的なスイーツと言えば、カステラが有名です。
私自身もこのスイーツを非常に気に入っており、コンビニで手軽に購入できるので、ついつい食べ過ぎてしまうことがあります。
しかし、皆さんはカステラの漢字での表記を知っていますか?
意外にも、この親しみやすいスイーツの漢字表記は少し複雑です。
そこで、今回はカステラの漢字での表記法やその背景、さらには中国語での表記についても掘り下げてみました!
カステラの漢字表記について
漢字でどのように表現されるのか?
カステラの漢字表記には様々なバリエーションが存在します。ここでいくつかの例を挙げてみましょう:
- 家主貞良
- 加須底羅
- 粕貞羅
- 春庭餹
- 角寿鉄異老
- 卵糖
これらの表記を見ると、驚くほど多様で、すべてが「カステラ」と聞くと少し信じがたいかもしれません。
表記の意味と由来
上記の五つの表記は、すべて「カステラ」に合わせて創られた当て字であり、特に意味は含まれていません。一方で、「卵糖」という表記は、当て字ではなく、カステラの主要な成分を意味的に表現しています。
カステラの漢字表記の背景
これらの漢字表記の背景にあるカステラの由来や、それが記載された文献についても深掘りしてみましょう。これにより、カステラというスイーツがどのように日本に根付いたのかが明らかになるかもしれません。
カステラの語源とその歴史
カステラが日本に伝わった背景
カステラは、16世紀に日本に伝わったとされています。このスイーツの名前は、多くの異説がありますが、最も有力なのはイベリア半島の旧カスティーリャ王国(Castilla)から来ており、ポルトガル語での発音「カスティーリャ」(Castella)が語源だとされています。
江戸時代に見られるカステラの当て字
江戸時代には、カステラを表す様々な漢字表記が存在していました。これらの表記は、主に音から連想される漢字を用いて創られました。
主なカステラの当て字表記とその由来
「家主貞良」の解説
最初に紹介するのは「家主貞良」です。この表記は、「家」が「カ」、「主」が「ス」、「貞」が「テ」、「良」が「ラ」と読まれます。特に「主」は通常「シュ」と読みますが、ここでは「ス」と読ませるために用いられています。この表記については、江戸時代の『諸国板行帖』という書物に記載があります。
「加須底羅」の解説
次に「加須底羅」です。「加」が「カ」、「須」が「ス」、「底」が「テ」、「羅」が「ラ」と完全に音読みで一致しています。この表記は『和漢三才図絵』に記載されており、非常にしっくりくる表記です。
「粕貞羅」の解説
「粕貞羅」は「粕」で「カス」と読み、「貞」で「テ」、「羅」で「ラ」とされます。「粕」一文字で「カス」と読むのは興味深い点です。この表記も『酒井様御菓子値段帳』に見られます。
「春庭餹」の解説
「春庭餹」という表記は、「春」で「カス」、「庭」で「テ」、「餹」で「ラ」と読みます。「春」は「春日部市(カスカベシ)」から、「餹」は本来「あめ」を意味し、「トウ」と読むことから少し無理がありますが、甘いものを表すために使われています。この表記は『古今名物御前菓子図式』にあります。
「角寿鉄異老」の解説
最後に「角寿鉄異老」です。「角」が「カ」、「寿」が「ス」、「鉄」が「テ」、「異」が「イ」、「老」が「ラ」と読まれます。「老」を「ラ」と読むのは少し強引ですが、この表記も『原城紀事』に記載されています。
「卵糖」という表記の起源
夏目漱石による独自の表記
これまで見てきた「カステラ」の表記は、主に当て字で表されてきましたが、明治時代に入り、新たな表記が提案されました。この提案を行ったのは、日本の文豪・夏目漱石です。彼は1907年に発表した作品『虞美人草』の中で、以下のような表現を使いました。
チョコレートを塗った卵糖(カステラ)を口いっぱいに頬張る。
卵糖の表記の意味
「カステラ」は主に卵、小麦粉、砂糖を使って作られることから、「卵糖」という表記が考えられました。この表記は、カステラの主要な成分を反映しており、意味的には非常に適切です。しかし、実際にはこの表記が広く採用されることはありませんでした。
現代における「卵糖」の使用状況
理由としては、漱石が実際に「カステラ」を指して「卵糖」と表記したのではなく、一般的なスポンジケーキを指していた可能性が高いとされています。そのため、この表記は一般的なカステラの表記としてはあまり認知されていないのが現状です。
カステラの中国語表記について
日本語と中国語の漢字表記の違い
これまで日本語でのカステラの漢字表記に焦点を当ててきましたが、隣国中国での表記も非常に興味深いものがあります。
カステラを表す中国語の漢字
カステラの中国語での表記を調べたところ、「蛋糕」という漢字が使用されています。この表記は少し複雑に見えるかもしれませんが、その意味を詳しく見ていきましょう。
意味と発音の解説
「蛋糕」の発音は「ダンガオ」となります。1文字目の「蛋」は「卵」または「卵形のもの」を意味し、2文字目の「糕」は「(小麦粉などで作った)菓子」を表します。この二つの漢字を合わせると、「卵と小麦で作った菓子」という意味になり、これが日本語の「カステラ」に相当します。
カステラとケーキの表記が同じ理由
興味深いことに、中国語では「ケーキ」と「カステラ」が同じ「蛋糕」で表記されます。これは、両者が似た材料と製法で作られるため、中国語では区別せず同一の語を用いることが多いのです。
まとめ
以上がカステラの漢字表記に関する解説です。ここで簡単におさらいしてみましょう。
カステラには「家主貞良」、「加須底羅」、「粕貞羅」、「春庭餹」、「角寿鉄異老」、「卵糖」といった多様な漢字表記が存在します。
このお菓子の名前の由来としては、ポルトガル語の「カスティーリャ(Castilla)」が有力です。
また、「家主貞良」や「加須底羅」などの表記は、全て当て字であり、これらは江戸時代の文献にその記録が見られます。
「卵糖」は夏目漱石が考案した表記で、実際にはスポンジケーキを指しているとの指摘もあります。中国語では、「カステラ」は「蛋糕」と表記され、「ケーキ」と同じ意味を持ちます。
カタカナの4文字からこんなに多くの漢字表記が派生しているのは驚きです。
これを使って、「今日のおやつは『家主貞良』、さて何でしょう?」と子供にクイズを出すのも楽しいかもしれませんね。